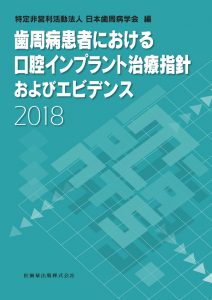アクアデンタルクリニック院長の高田です。
「歯周病患者における口腔インプラント治療指針」
を読みました。
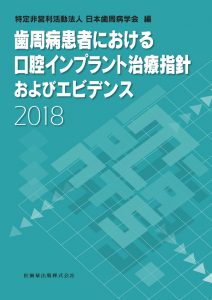
学んだ内容
歯周治療におけるインプラント治療の位置付け
歯周病思者にインプラントを理入した場合.インプラント治療は高い成功率を示すが.
10年以上の長期観察では歯周既往のない者に比べて生存率はやや劣ることも示されてい
る.
とくに.定期的なメインテナンスに応じない歯周病患者では喪失率が高くなる
これらのことから-歯周病はインプラント治療予後のリスク囚子と考えられ.
歯周病の厳密なコントロールが必要である。
したがって歯周病思者では大然物からの感染リスクを最小限にするた
め.インプラント理入前には可能な限り徹底した歯周病治療を行うことを原則とすな
☆インプラント体の選択☆
現在様々なタイプのインプラントが製造・販売されている.インプラントの長さ.
長さ 太さ.形状.インプラントシステム(表面性状を含む)を考慮し使用するインプラントを選択する.
⑴長さ
一般的に8~13mm程度の長さのインプラントをⅢいることが多ぐ
解学的な制約を考慮して選択する。
近年は8mm以下のショートインプラントでも良好な結果が報告されてお
り.高度な骨吸収によって上顎洞や下歯欟管が近接した患者では有用である。
しかし周囲骨に吸収が起こり.クラウン-インプラントレシオが悪化した際.
ショートインプラントではインプラントの安定性が損なわれる可能性がある.
このような点を考慮し症例に適した長さのインプラント体を選択する必要がある。
(2)太さ
一般的には直径3.5~50mmのものが用いられている。
とくに.歯周病患者では骨吸収か進行していることが多く
水半的に小化した顎堤では35mm以下のナロータイプを用いることで.
骨造成を回避することができる.
しかしインプラント幅径が小さいと破折のリスク
が上昇することが考えられるのでを歯種.咬合力の大きさ.咬合様式を考慮する。
(3)形状
インプラント体の形状は血が平行なパラレルタイプと尖端が先細りのテーパードタイプに
分類される。パラレルタイプは埋人窩の形成が簡便で.埋入深度の調節が容易であるが.
骨質か不良な場合.十分な初期間定が得られにくい
一方.テーパードタイプは.多種類のドリルを必要とし、埋人深度の調整か難しい.
しかし埋人時に周囲骨を圧退するため.軟らかい骨であっても十分な初期閤定を得やすい
(4)インプラントシステム(インプラント表面性状を含む)
インプラントシステムによってインプラント表面性状.インプラント形態.
コネクション機構などが異なる。
インプラント表面性状は機械研磨 中等度粗面、粗面の3種類に大別される。
2015年に報告されたシステマティック・レピュー
では5年以上のインプラント予後にインプラント表面性状が及ぼす影響を調べている。
その結果、上顎においては機機研磨よりも中等度粗面のインプラントの方が生存率は高かった
下顎では差が認められなかった。
また.インプラント周囲の骨吸収は理入後1年以内に起こることか多く、
骨吸収程度はインプラントシステムによって異なると報告された.
最近のコクランシステマティックレピニーでインプラントシステムの違いが
臨床成績におよばす影響を検証し
「特定のインプラントシステムが優れた臨床成績を示すという工ビデンスは存在しない」
と結論づけている。
しかしインプラント周囲骨に吸収が起こった場合.表面性状が粗であると
プラークリテンションファクターとなりやすいため.
歯周病患者で慎重にインプラントシステムを選択すべきである
埋入時期の選択
抜歯からインプラント入までの期間は,抜歯かの治癒や周囲軟・硬組の変化に物して
4つに分類される
歯周病患者では歯周病の原因か除去されたことを再計価で確認後.インプラント治療を行う
ことが原則なため.Typel(抜齒即時埋入)を選択することは限定される.
とくに.抜歯カが大きぐ上顎洞や下知管などの解制学的制約を有する上下大臼歯では低リスクかっ初期
間定を得やすいTy3(抜齒窩の封鎖確認後)以降の理入を選択することか多い
4)荷重時期の選択
咬合力の荷重時期は.即時荷重.早期荷重.通常荷重の3つに分類される.通常荷重とは確
実なオッセオインテク・レーションを得るための免荷期間(埋入後2カ月以上)を経てから行う
荷重を行う方法である。
一般的には.「初期間定か不良な場合(埋人トルクく30Nなm)」.「大
きな骨造成を伴う場合」.「パラファンクションを疑う思者、
「ショートインプラント」.「全身的なハイリスク思者」では
即時荷重ならびに早期荷重は禁忌である.
治療法に1回法(non-submerged)と2回法(submerged)に区別される。
一回法では埋入手術治を確認して上部構造製作に移行するのに対し2回法では一次手術としてイン
プラント体の埋入.二次手術としてアパットメントの連結を行う.
1回法は.すべての荷重時期の適応が可能であるのに対し
2回法では早期荷重もしくは通常荷重を選択することとなる.
2回法はインプラント体とアバットメント間のマイクロギャップによってインプラント周囲炎
による骨吸収が1回法より起こりやすいと報告されていたが、
現在では差はないとされている。
また.インプラント体のプラットフォーム径より小さい径のアパットメントを装着(プラッ
トフォームスイッチング)することで.インプラント周囲と骨頂の歯骨の吸収が予防され.
齒肉退縮を防止できることか報告されている。
歯周病想者では.埋入後初期感染の危険性か低い方法の選択が勧められるため.2回法で通
常荷重を選択することが多い。
歯周基本治療において経口抗菌療法は臨床的に有効か?
歯周病原細菌の感染を伴う重度広汎型歯周炎患者の深いポケットに対して従来の歯周基本
治療(プラークコントロール,スケーリング,ルートプレーニング)に加えて,
経口抗菌療法(テトラサイクイン系,マクロライド系,ペニシリン系)を併用することにより
,臨床的および細菌学的に付加的な改善効果が期待できる.
このことから,歯周基本治療において従来の治療法に加えて感染の診断に基づいて経口抗菌療
法を用いることが検討されるべきである.
背景,目的
従来の歯周基本治療では,重度進行性の歯周炎に対して,治療効果が限られたものであるこ
とが示されている.
一方,経口抗菌療法が従来の治療法と併用されているが,その治療効果
については,必ずしも一致した結論が得られていない.
2004 年までのシステマティックレビューやコンセンサスレポートによれば,
歯周治療における経口抗菌療法は,特に侵襲性歯周炎や重度慢性歯周炎患者の深いポケット(PD 6 mm 以上)
に対して臨床的改善効果が期待できることが示されてきた.
しかしながら,経口抗菌療法を歯周治療に応用する際の疑問として以下の点が指摘されている.
�1 どのような患者に経口抗菌療法を行うべきか?
�2 どのような抗菌薬あるいはその組み合わせが有効か?
�3 適切な抗菌薬の投与量,投与期間,投与時期について
�4 誤った薬剤の使用による治療反応性の低下について
�5 抗菌薬投与の副作用や耐性菌の増加について
である.ここでは,歯周基本治療における経口抗菌療法の適応症と適応時期および臨床的効果
を中心に,2007 年までに報告されているランダム化比較試験を主とした臨床研究報告とシステ
マティックレビューにコンセンサスレポートや総説を加えて,上記の疑問に関する見解を示す.
経口抗菌療法の適応症と期待される臨床的効果
従来の歯周基本治療で反応性が良好な歯周炎に対しては,経口抗菌療法の付加的臨床効果は
あまり期待できない.
一方,治療反応性(深いポケットにおける PD 減少効果,部位率の減少効果,
プロービング時の出血の減少効果など)が不良な重度広汎型の歯周炎症例(歯周病原細
菌の感染を伴う深いポケットの部位率が 20~30%以上の慢性および侵襲性歯周炎患者)および
喫煙,血糖コントロール不良,冠動脈疾患を有する中等度から重度歯周炎患者に対する細菌検
査に基づいた経口抗菌療法の応用は,
臨床的に有意な改善効果が認められている.
期待される治療効果は,深いポケットの 1 mm 程度の付加的減少やその部位率の 20~30%程度の付加
的減少および細菌学的効果の持続などである.
最近のランダム化比較試験研究では,広汎型侵襲性歯周炎患者を対象とした
経口抗菌療法の有効性が評価されているが,侵襲性歯周炎と慢性歯周炎での臨床的効果の差異を示した報告はなく,
病態による診断分類が経口抗菌療法の選択基準とはならない).
広汎型重度歯周炎,従来の治療法に対する治療反応性不良部位を多く有する症例に対しては,
経口抗菌療法の有効性が示唆されている.喫煙患者に対しては,抗菌療法を併用することにより,
非喫煙患者および禁煙患者と同程度の臨床および
細菌学的効果が期待できる.血糖コントロールが不良な糖尿病患者に対しては,抗菌療法の
併用が血糖コントロールの改善に有効と考えられているが,従来の治療法と比較して有意な差
異は認められていな).また,重度歯周炎患者に対して,抗菌療法を併用することにより全身
的炎症状態が改善し,冠動脈疾患の発症リスクを低下させる可能性が報告されている